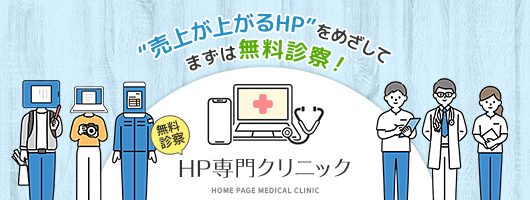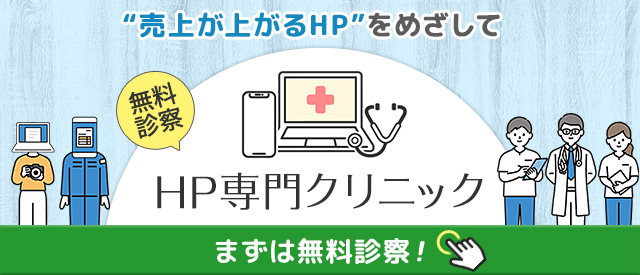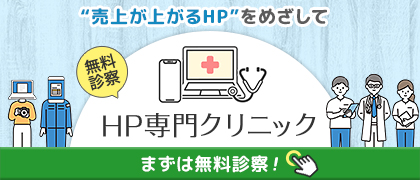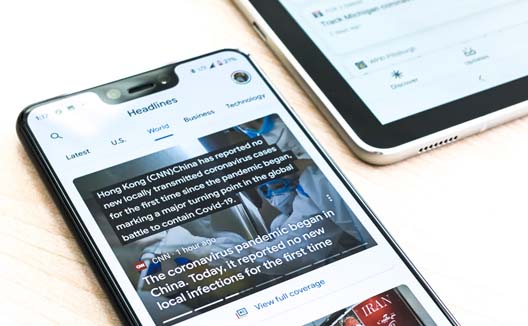
SEOトピックス
LINEの新フォント「LINE Seed JP」 を活用してみよう!
LINE(株)、およびフォントワークスは2022年10月24日、 LINEのオリジナルコーポレートフォント日本語版の『LINE Seed JP』を、共同開発したことを発表しました。
『LINE Seed JP』は今後、LINEの事業活動やイベントなど、さまざまなシーンで使用されるとのことですが、一般にも公開して誰でも無料で自由に使用できるもの、としています。
今回は、“実際に”『LINE Seed JP』をWebフォントとして使ってみましたので、参考にしてみてください。
『LINE Seed JP』とは
2020年に、LINEよりブランディングの一環としてグローバルリリースされた、欧文コーポレートフォント『LINE Seed Sans』の日本語書体です。
収録内容は
ひらがな・カタカナ・漢字・数字・記号9,354字を収録しており、Thin/Regular/Bold/Extra Boldの4段階のウエイトがあります。
形式はTrueType/OpenTypeに加え、Web向けのWOFF/WOFF2/EOT形式が用意されています。
ダウンロードは以下から可能です。
『LINE Seed JP』の特徴
親しみのある“カドマル”ゴシック
角の丸み = 「カドマル」 が最大の特徴であり角ゴシック体よりも少しカジュアルで柔らかい、より親しみやすい書体です。
明るく、大人なモダンスタイル
親しみだけでなく、モダンで大人の印象もあります。“ふところ”を広く、仮名は曲線を多く取り入れられており、明るいモダン系のゴシック体です。
日本語ならではの美しさと整合性のバランス
今回は、日本語書体ということで、日本語ならではの美しさ、形の整合性(バランス)も非常に取れていると感じます。
この辺りは、既存の欧文コーポレートフォント『LINE Seed Sans』での統一されたジオメトリックなルールに基づいて開発されていたようですが、日本語書体ならではの美しさを目指すため、何度も検証を重ねられたそうです。
実際に使ってみよう!
では、ここで早速「LINE Seed JP」を使ってみます。
LINEの新フォント「LINE Seed JP」 を活用してみよう!
LINEの新フォント「LINE Seed JP」 を活用してみよう!
LINEの新フォント「LINE Seed JP」 を活用してみよう!
LINEの新フォント「LINE Seed JP」 を活用してみよう!
見やすくどこか親しみやすさを感じさせるフォントとなっています。
さらに、フォントのウェイトによって、与える印象も変わらないように工夫されていますので、
フォントウェイトによる使い分け
どうですか?印象は変わらないですね。
このように、印象を変えることなくメリハリをつけられるので、見出しや本本の統一性も保つことができます。
また、LINEならでは親しみやすさ、という点では以下のようにフキダシや語りかけ、チャット等に使うと効果的かもしれませんね。
こんにちは!このページでは「LINE Seed JP」について紹介するよ!
サイトでの活用
いかがでしたか?
『LINE Seed JP』のデザインは、LINEならではのフォントで、シンプルかつユーザーフレンドリーな印象を与える事ができます。
書体デザインディレクター 藤田重信さんはコメントで、『大人のひとが微笑んでいるような印象を持った文字」をイメージした』と仰っています。
特に合いそうなシーンは、
- BtoCのサイト
- 若者向けの商品やサービスを取り扱うサイト
- SNSのような人とのコミュニケーションコンテンツがあるようなサイト
- 重厚よりもライトでフレンドリーなイメージのサイト
等ですが、皆さんのサイトの種類や取扱コンテンツ、ターゲット層やペルソナに合わせて活用してみてください。
もちろん、弊社でもこういったものを取り入れながらお客様にはご提案しておりますので、お気軽にご相談ください。
関連記事
- 2026.01.30
- AIとSEOの関係はどうなる?検索エンジンの未来予測
- 2025.12.26
- AIが変える検索行動!企業が準備すべきこととは?
- 2025.12.24
- AIモードで変わる検索体験!今後の中小企業のWEB戦略とは
- 2025.12.22
- SEOとは?検索エンジン最適化の基本から実践まで
- 2025.12.15
- AIモード対応とは?押さえておきたい最新WEBサイト制作のポイント
- 2025.11.27
- SEOはもう古い?誤解の原因と最新のSEO対策について解説
- 2025.11.17
- LLMOとは?AI検索の特徴と、チャンスを増やす方法
- 2025.10.28
- SEOにも効果大!「強み」が伝わるホームページ制作のポイント
- 2025.10.03
- 生成AI時代のマーケティング戦略
- 2025.08.22
- AIとは何なのか?種類からディープラーニングまで解説!